|
一度目の最高裁判決(第一次上告審判決)は、阿藤周平さんに対する死刑、その他三名に対する懲役刑を破棄し、広島高等裁判所へ差し戻した(吉岡は上告を取り下げ、服役した)。
二度目の最高裁判決(第二次上告審判決)は、四名全員に対する無罪判決を破棄し、またまた広島高等裁判所へ差し戻しになっている。
同じ事件を巡って有罪と無罪に最高裁の判断が分かれただけに、マスコミと人々の注目をおおいに集めた。
一九六八年、裁判史上稀に見る三度目の最高裁判決が言い渡された。最高裁は原判決を破棄し、被告たちに無罪を言い渡した。異例の破棄自判。
「いつもなら、上告で破棄する場合でも、自判などせずに、いちおう下級裁判所に差し戻しにするのが通例である。犯罪事実の黒白に関する誤判を問題とする上告に対し、書面審理を原則とする最高裁が、直接の審理もせずに、自判によって原判決を変更することは出すぎたことで、無謀だとさえいわれていたのである。
したがって、八海事件第三次上告審の場合、弁護側でも破棄して自判で無罪にすることは、希望としてはもっていたが、実際問題としては三度目の破棄差し戻しにされても満足すべきものと覚悟していたのだ」
と、その日の心境を弁護団の一人であった故正木ひろし弁護士は、自らの著書『八海裁判』で記している。
これで晴れて四人の無実は証明された。
広島拘置所にいた阿藤さんは、どんな気持ちでこの日を迎えたのであろうか。
|
「八海判決、ついに来た。
この日を私は万感をこめて待った。
苦しい日々であった。
辛い日々であった。
昨夜は、なかなか眠れなかった。
うとうとしたと思うと目がさめ、まんじりとしない一夜、朝、暗いうちから目はぱっちり開いた。
無罪を受ける日、
絶対!無罪を信ずる。何だか胸がしめつけられる思い。
無罪。青天白日後のことを、あれこれと心に描く、この胸は高なる。
血わく。
私は信じて判決を待つ、無罪を確信する。 (午前一〇頃記)
私は最高裁の大法廷を瞼に描いてみる。
まるで手にとるようにして、大法廷のもようがわかるようだ。
午前一〇時三〇分、奥野裁判長より、おごそかに絶対的判決が言渡される。
奥野裁判長は、りんとした声で無罪を宣告されると確信する。
いま午前一〇時をすぎた頃であろうか。
女房が則生の手をひいて大法廷に入る姿を描いてみる。
まき子よ、まき子の心の中に私がいる。
青天白日
無罪判決の報を待つ。
刻一刻と判決言い渡しの時刻が迫まるにつれ、緊張は続く。
はりつめた心、
無罪を確信する心、
何とこうまで、私の心をとらえてはなさないのであろう。
十八年間血を吐き出すような真実の訴えが、今日後数分後に報いられようとしている。
天にものぼる気持である。神よ、正義をたれ給え。」
(阿藤さんの手記・・・佐々木静子著『もえる日日』から)
|
午前10時30分、最高裁判所第二小法廷・奥野健一裁判長が読み上げた判決文は、「原判決を破棄する。被告人らはいずれも無罪」だった。この無罪判決は、第二小法廷の裁判官五人全員一致によるものだった。
判決が言い渡された瞬間、法廷では、阿藤さん以外の三名の被告とその家族、そして阿藤さんの奥さん、弁護団が「よかった、よかった」と歓声をあげ涙を流していた。
この報はいち早く広島拘置所に届いた。阿藤さんは、一人独房の中で運命の時を待っていた。
「東京から拘置所へ電話があったんでしょうね。無罪判決がおりたから支度しておくようにと、すぐさまドアを開放してくれたんです。ただ、まだ正式な書面が来ないから。それまで整理しておくようにと言われて」(1998年9月5日、阿藤さん談)
主犯格とされていた阿藤さんの身柄はこうして解放された。その時、阿藤さん、42才。24才で逮捕されて以来、長い年月をこの裁判に費やしてきた。阿藤さんはのちにこう語っている。
「無罪判決までの時間は『重み』だった。人生としては、いい勉強になった。無罪判決から今までは、何をして生きてきたんだろうなあ。経ってみれば早い。でも、尾は引いている。今でも(八海事件のことを)言われることはあるし、忘れたことはない。ぼんやりしていると、昔をふり返る。思い出すのはあの苦しみ。よく耐えられたなあと思う。孤独の中で生きてるんだけど、とにかく体の不自由とか自由を束縛されている以上の、それ以上の怒りを持っていた。苦しみがあった。信用されない、真実が裏切られた、その怒りで生きてきたんじゃないかなあ」(1997年12月23日、阿藤さん談)
この八海事件を世に広く知らしめた映画がある。阿藤さんたちの無実を世の中に訴えた正木ひろし弁護士の著書『裁判官』を映画化した『真昼の暗黒』(今井正監督)である。
この映画によって、八海事件の真相が広範な人々の目に触れ、阿藤さんたちへの支援の輪が大きく広がった。
「この映画を見たという人から、一日に多くて50通から60通も、頑張ってくださいという激励の手紙が届い」たという(1997年12月23日、阿藤さん談)。
私がこの映画を初めて観たのは、富山集会(1989年11月)でのことだった。もう12年も前になる。集会開始時間より遅れて会場に入った私は、部屋が暗くてびっくりした。ちょうど『真昼の暗黒』の上映の最中だったのだ。暗闇の中から一つだけ席を見つけそこに座り、映画を凝視していると、右隣に座っていた男性が泣いているように感じた。私もこの映画を観ていて、こんな恐ろしいことが現実に起きたのかとまず驚き、次にえん罪をかけられた人たちの境遇を思い悲しい気持ちになっていた。
この映画のラストシーンは、第二審・広島高等裁判所での有罪判決直後の面会で、被告の母が悲しみのあまり何も語れず、絶望に満ちて涙しながら面会室を出ていこうとする後ろ姿に向かって、「おっかさん! まだ、最高裁判所があるんだ! まだ最高裁があるんだ!」と阿藤さん役の主人公が叫ぶシーンで終わっている。阿藤さんにとっては最高裁判所が最後の砦であったに違いない。
映画が終わり、司会の方から「この映画の主人公である阿藤周平さんにお話をお願いします」と紹介があると、タイミングよく隣の男性が立ち上がった。私は「トイレにでもいくのかな?」と思っていた。すると、その人は会場の正面に向かって歩いていくのである。そしてふり返り、「こんにちは、阿藤周平です」、そうあいさつしたのだ。まさか、隣の男性が阿藤さんだったとは、思いもよらなかった。
この集会が縁で、私は今日、阿藤さんとも、富山事件とも関わることになった。
映画の中では、八海事件の持つそれぞれの人間模様が実によく描写されている。吉岡晃が単独犯から複数犯へ供述を変える場面、供述の変転、阿藤さんたちへの拷問、自白の強要、偽証罪のデッチあげ等である。
事件の起きた熊毛郡麻郷村字八海とは、どんなところなのだろうか。私は1999年に一度、足を運んでみたことがある。
現在、麻郷村字八海は田布施(たぶせ)町になっている。田布施町は山口県南東部に位置し、街の北西部は山岳地帯となっている。この山岳に源をなす小河川が合流して八海川(現田布施川)となり、街の中央部を貫流し瀬戸内海に注いでいる。政治家岸信介・佐藤栄作兄弟宰相出身の地としても知られている。
映画では暗く描かれざるを得なかった街だが、私には瀬戸内の温暖な気候と豊かな自然に恵まれた開放感のある静かな街のように思えた。
さっそく八海橋に行って見る。すると、「この先の橋梁(旧八海橋)は老朽により全面通行止」の看板が立っていた。見るとすぐ側の国道188号線上に新八海橋があり、その橋を車が次から次へと走り去っていく。旧八海橋では、男性が一人、橋の中央あたりで釣り糸をたれていたが、もはや、この橋を渡ることはできないようだ。この八海橋を田布施町側から渡ると阿藤さんの住んでいた平生町となる。
私は八海橋を眺めながら、映画『真昼の暗黒』のあるシーンを思い起こしていた。
一人の被告の家族(母と叔父)が、平生町の方からこの橋を渡ってくるシーンである。
叔父に「清水(仮名=注)のおふくろさんは、裁判所でちゃんと罪が決定してるのに、いまだに『うちの息子は悪いことはしとらん、しとらん』とふれ歩いている。そんな暇があったら、たとえ線香の一本でも持って被害者の仁科さんち(仮名・被害者宅)に謝りにでも行く方が本当の人間の道だとな、みんなそう言っている」「やったとか、やらんとか、そんなことを言ってやせん。ただ、おまえらみたいに、裁判が間違ってる、検事がどうの、いや判事がどうの、そんな生意気なこと言ってるより、線香の一本でも持って仁科さんちへ悔やみに行った方が世間の同情があるって言ってるんだ」と言われ、その叔父と母の二人で、被害者宅に線香とお供え物を持って謝りに行こうとする場面である。しかし、母親は橋の途中までくると、急に立ち止まり、「やりもしないものを、どうして謝りになんか」と言って、そのお供え物と線香を八海川に投げ捨て泣き崩れるのである。
映画の中でも非常に印象的だった場面だが、被告同様、家族もまた苦しみもがいていた。この母親は八海橋をどうしても渡りきることはできなかったんだろうなあと思いながら、私はこの地をあとにした。
(注・映画では、被告たちをはじめ名前はいずれも実名ではなく、八海橋も「三原橋」とされている。)
無罪が確定した最高裁判所の前で、正木ひろし弁護士はこう演説している。
「現在の司法権、裁判制度、そういうものをおいといていいかどうか、我々は単なる被告たちだけを救うのでなく、日本の文化のこういった病気を、根性の悪さを、官権の横暴と、怠け者と、月給泥棒とを早くやめさせると、被告を苦しめた奴は恩給を取り上げると、場合によっては、司法殺人の未遂者であるとして皆さんの国民裁判にかけるまで行かなければ本当の解決ではないということを申し上げます」
そして無罪確定から33年が経った今、果たして本当にえん罪事件はなくなったであろうか? 答えるまでもなく、いまだにえん罪は絶えることはない。にもかかわらず、警察官も検察官も裁判官も、「司法殺人」として裁かれた者は誰一人としていないのである。正木弁護士の指摘は、今日においても問われ続けている。
今年の1月24日、八海事件は事件発生から数えて半世紀となる。この八海事件の裁判記録を残そうとする動きが最近出てきている。
「『二度とえん罪を起こさないために活用してほしい』、故正木ひろし弁護士の手紙など『八海事件』をめぐる朝川広男さん(74才)収集の資料が21日広島大総合科学部の伊藤護也研究室に寄贈された」
(2000年1月22日/朝日新聞・広島版)(「かちとる会」ニュース137号に掲載)
これを受けて、広島では、この春にも、関係者の間で映画『真昼の暗黒』の上映や阿藤さんたちに体験を語ってもらうなどの記念事業を開催することを発表している。阿藤さんはぜひ若い人たちに八海事件のことを知ってもらいたいとコメントしている。
若い世代が昔話としてこの八海事件を聞くのではなく、現在(いま)の問題として認識していかなければならないのではないだろうか。そうでない限り時間の経過と共に忘れ去られることになると思うからである。
この春に行われる集会には、ぜひ私も参加したいと思っている。 (うり美)
|
![]()
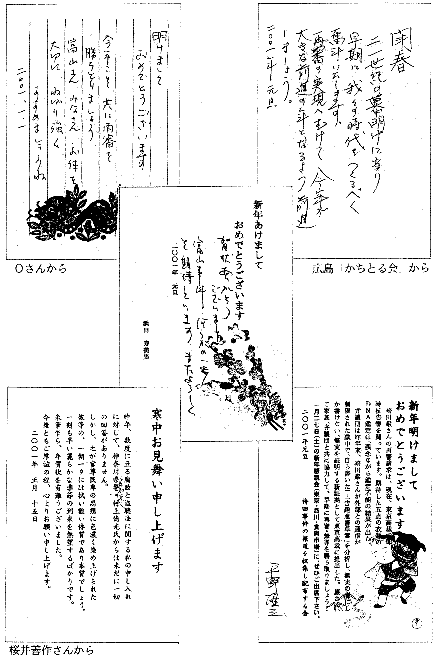
![]()

 今からちょうど50年前にあたる1951年(昭和26年)1月24日。山口県熊毛郡(くまげぐん)麻郷村(おごうむら)字八海(やかい)で、瓦製造業を営む老夫婦が惨殺され現金約1万6000円が盗まれるという事件が発生した。事件はあたかも夫婦げんかのあげく、妻が夫を殺し、その後首吊り自殺をしたかのように見せかけていたが、殺人事件であるということを疑うものは誰もいなかった。
今からちょうど50年前にあたる1951年(昭和26年)1月24日。山口県熊毛郡(くまげぐん)麻郷村(おごうむら)字八海(やかい)で、瓦製造業を営む老夫婦が惨殺され現金約1万6000円が盗まれるという事件が発生した。事件はあたかも夫婦げんかのあげく、妻が夫を殺し、その後首吊り自殺をしたかのように見せかけていたが、殺人事件であるということを疑うものは誰もいなかった。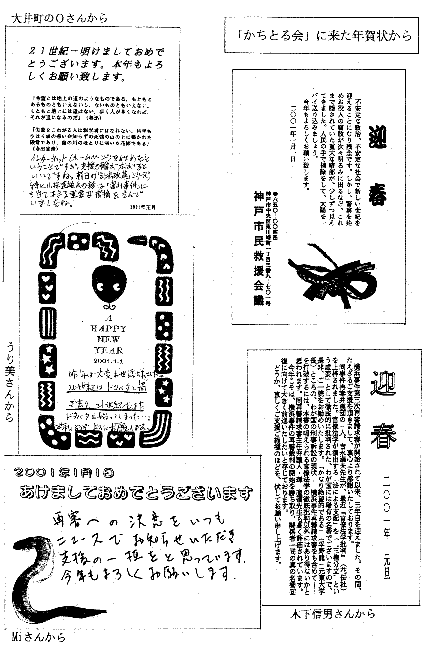
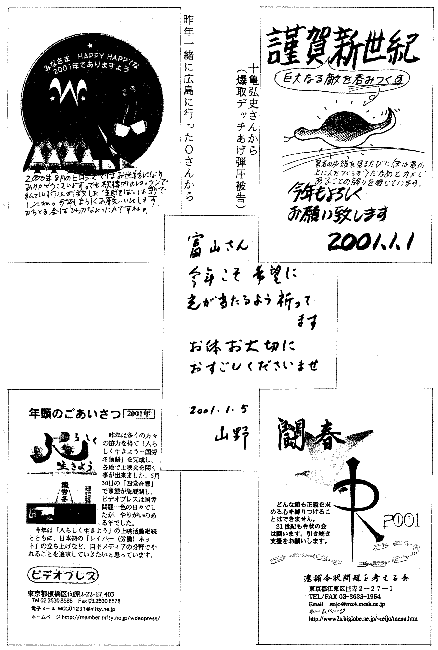
 やっと双方向の態勢がとれました。ホームページを開設しながらメールアドレスが無いという奇妙な状態に終止符、どしどしお便りください。といっても御存知のとおり「五十の手習い」でどこまでお応えできるか保障の限りではないというのが実状ですが、なんとか努力しますのでよろしくお願いします。なんて殊勝なことを言っているが簡単にメールはこなせると思っているに違いない、といつも私をいじめるやさしい(!)女性達がのたまう声が聞こえるようです。叱咤激励ではなく叱咤ばかりだなどといじけないで、素直に激励とうけとってがんばります。 (富山保信)
やっと双方向の態勢がとれました。ホームページを開設しながらメールアドレスが無いという奇妙な状態に終止符、どしどしお便りください。といっても御存知のとおり「五十の手習い」でどこまでお応えできるか保障の限りではないというのが実状ですが、なんとか努力しますのでよろしくお願いします。なんて殊勝なことを言っているが簡単にメールはこなせると思っているに違いない、といつも私をいじめるやさしい(!)女性達がのたまう声が聞こえるようです。叱咤激励ではなく叱咤ばかりだなどといじけないで、素直に激励とうけとってがんばります。 (富山保信)